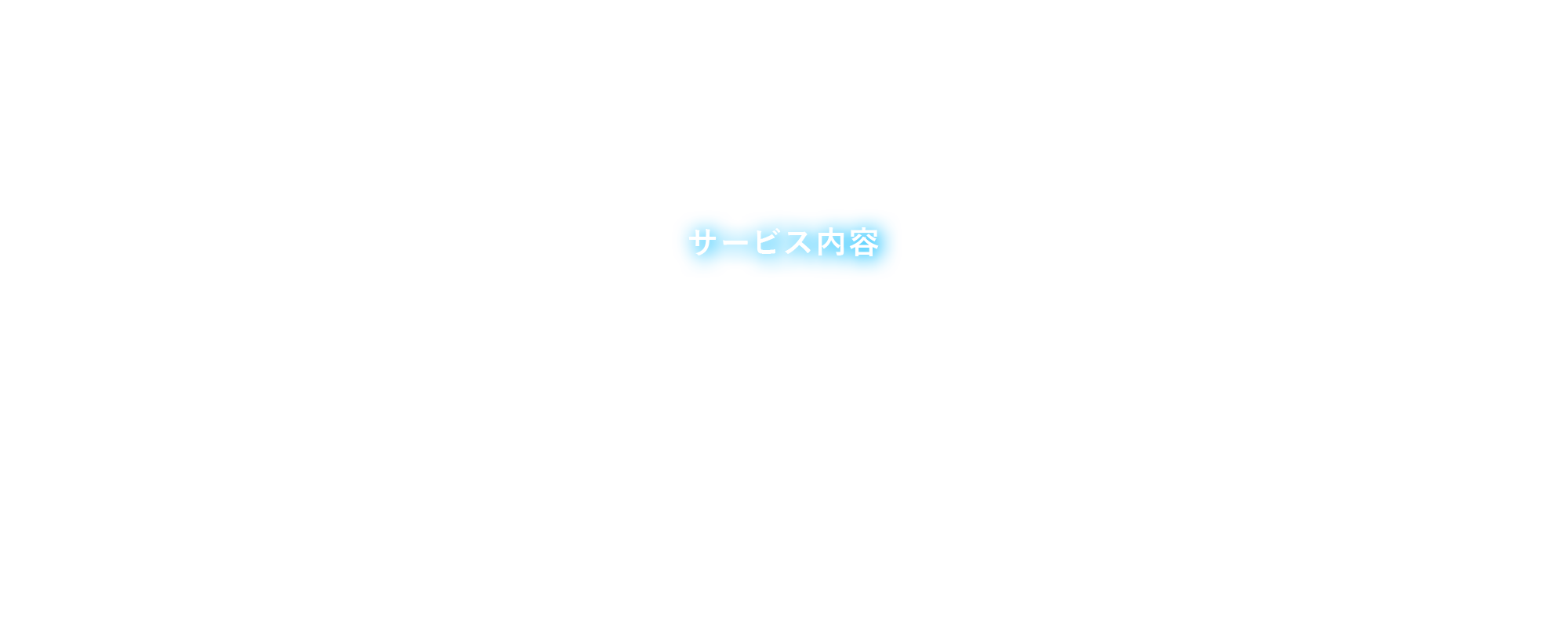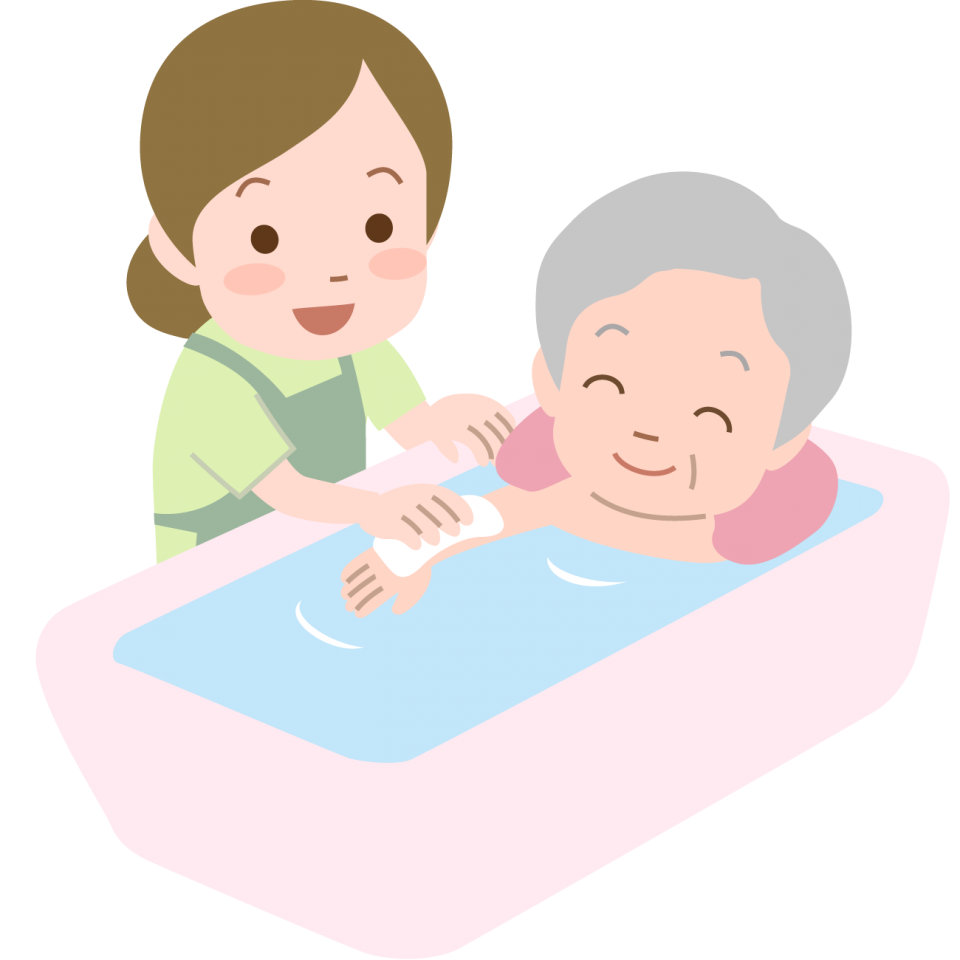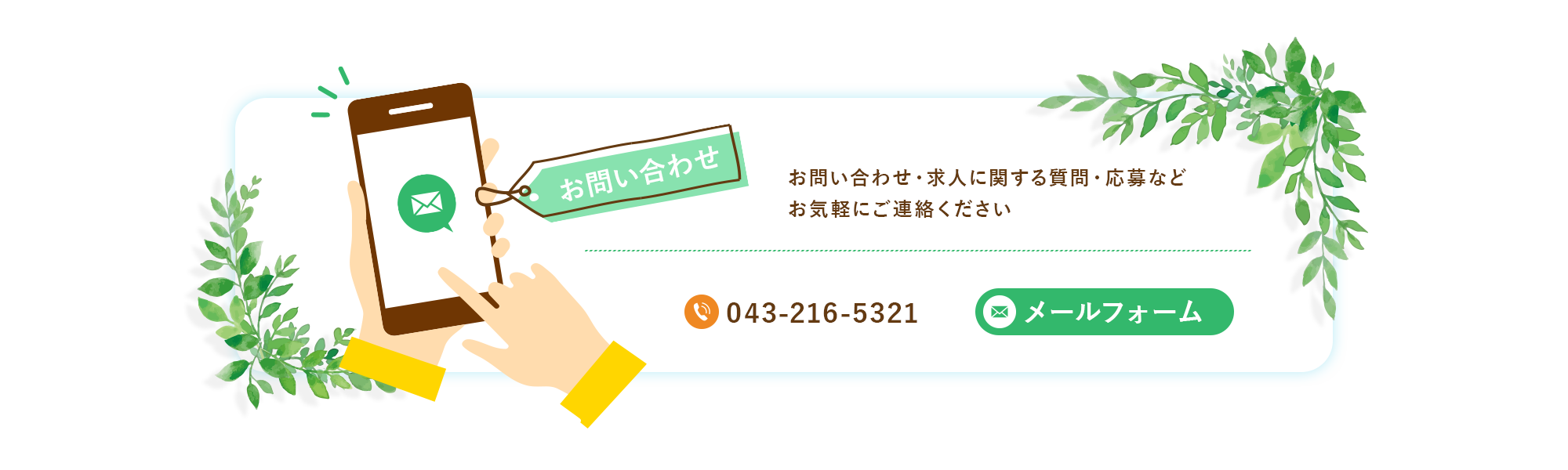高齢者訪問介護
65歳以上で要介護認定を受けている方が対象の訪問介護サービスです。
自立が難しい利用者様の生活の負担軽減を目的として、身体介護・生活援助を行います。
訪問介護対象者のご案内
訪問介護対象者のご案内
高齢者訪問介護サービスをご利用いただくにあたり、お住まいの区市町村で「要介護認定(要支援認定を含む)」を受ける必要があります。
要介護認定を受けるためには同区市町村の窓口に申請が必要です。認定レベルによって受けられるサービスが異なるためご確認をお願いしております。また、65歳以上の方は「要介護認定」を受けていなくてもご利用いただけることもあります。
詳しくはお住まいの区市町村窓口にお問い合わせください。
ケアマネージャーがついている方
当サービスには、ケアマネージャー(介護支援専門員)によるケアプラン(サービス計画書)作成が必要となります。担当のケアマネージャーがついていない方は地域包括支援センターもしくは、指定を受けた居宅介護支援事業者へご相談ください。
※要介護・要支援の認定レベルにより申請先が異なります。
サービス内容のご案内
生活援助
利用者様が日常生活を送る上で重要となる家事の援助の主な内容です。利用者様が一人暮らしである場合やご家族の負担軽減を目的とした補助サービスです。
詳細は下記のとおりです。
買い物・調理・配膳・洗濯・掃除・衣類の整理など。
薬の受け取りなどに関わる介助。
その他(相談・助言・情報提供など)
介護保険サービスについて
介護保険サービスでは、できることとできないことが介護保険制度により明確に定められております。そのため、ホームヘルパーとしてお手伝いできることには制限がございます。補助が難しい事柄に関しては利用者様の状況などにより異なりますので、ご利用になる前に利用者様に合わせて詳細なご説明いたします。ホームヘルパーによってお手伝いできること・できないことを知っていただくことで、お互いにトラブルを避けながらも適切な対応が可能となりますのでご協力をお願いいたします。
STEP 1要介護認定の申請
介護サービスを利用する方は、お住まいの区市町村の窓口または福祉事務所などに被保険者本人か家族が申請します。
(ケアマネージャーによる代行申請も可能です)
STEP 2訪問調査
役所より認定調査員がご自宅などを訪問し、心身の状況の調査として利用者様本人やご家族の方との面談や家庭環境の確認などを行います。訪問日程は事前に日程を確認されます。
STEP 3主治医意見書の作成
保険者(区市町村)が本人の主治医に、心身の状態についての意見書を作成してもらいます。特に決まった主治医のいない方は区市町村の窓口に相談します。
STEP 4認定結果の通知
要支援・要介護1~5までの6段階より認定されます。判定の結果、自立していて介護保険の対象ではない方は「非該当」となります。認定結果通知書と新しい被保険者証が送られてきます。
STEP 5ケアプランの作成
要介護度が認定されたら、ケアマネージャーを選び契約します。ケアマネージャーに依頼してケアプランを作成してもらいます。
ケアプランに基づいて、サービス事業者を選定します。訪問介護か通所介護などのサービスをどの業者に頼むかは、利用者や家族が決めます。どの業者を選んでよいかわからない場合は、ケアマネージャーに適当な候補をいくつか提案してもらいます。
STEP 6サービス業者の決定と契約
サービス事業者との契約は事業者ごと、サービスごとに契約をします。1つの事業者から2種類のサービスを提供してもらう場合は、契約は2件となります。
STEP 7介護サービスのご利用
ご契約が完了しましたら利用スケジュールにあわせてスタッフが派遣され、介護サービスをご利用いただけます。ご利用中のご質問は担当スタッフより受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
生活援助
利用者様が日常生活を送る上で重要となる家事の援助の主な内容です。利用者様が一人暮らしである場合やご家族の負担軽減を目的とした補助サービスです。詳細は下記のとおりです。
買い物・調理・配膳・洗濯・掃除・衣類の整理など。
薬の受け取りなどに関わる介助。
その他(相談・助言・情報提供など)
※2人のホームヘルパーにより訪問を行った場合
1人のヘルパーによる介護が困難と認められる場合等で、利用者の同意のもと2人のヘルパーでサービスを提供した場合は、2倍の利用者負担額をいただきます。
※ 者負担額の上限等について
介護給付費対象のサービス(ホームヘルプサービス、デイサービス、ショートステイ)利用者負担額は、市町村が上限を定めています。そのため、これらのサービスのご利用状況により、当事業所への月々の利用者負担額は変わることがあります。本事業者が代理受領を行った介護給付費額は、利用者に通知します。
※償還払い
介護給付費額を事業者が代理受領を行わない場合は、市町村が定める介護給付費基準額の全額をいったんお支払いいただきます。この場合、利用者に「サービス提供証明書」を交付します。「サービス提供証明書」と「領収書」を添えてお住まいの市町村に申請すると介護給付費が支給され
ます。